マスクや保護眼鏡などを装着しないで農薬散布をしている人を見ると、心配になりますが、散布者の安全対策は大丈夫でしょうか。
農薬散布時の事故は少数ながらも毎年発生しています。しかしそれらは正しい保護具の着用や農薬の取扱い時の注意によって防げるものです。農薬のラベルに表示されている「安全使用上の注意」に従って保護具を着用して散布してください。
農薬は製品や有効成分によって安全性に差があります。そのため、接触や吸入により健康に影響が出る場合がありますので、農薬の散布者は中毒やかぶれを起こさない為にもそれぞれの農薬の毒性に合わせた防護装備をして散布作業をする必要があります。農薬の種類により着用すべき防護装備等が異なりますので、それぞれの農薬のラベルに表示されている「安全使用上の注意」に従って保護具を着用して散布してください。また、散布終了後は身体・衣服に付着した農薬をきれいに洗い落してください。
農薬との接触を避けるため
農薬に直接触れることの多いのは、実際に散布をする作業者です。たとえば、散布作業では空中に漂う農薬の微粉末や霧を吸い込む可能性がありますし、準備の為に高い濃度の農薬を水で薄めたり、あるいは容器や散布機に移したりする作業で薬剤に接触することがあります。この為、出来るだけ接触を避けるようにマスク等の保護具や防除衣を着用する必要があります。なかでも毒性の高い農薬では、体内に取り込まれる量が許容できるレベルを上回らないように防護する事は必須です。一方、毒性の低い農薬では必ずしも完全重装備をする必要はありません。使用する農薬の毒性に応じて、散布場所、散布方法、散布面積、剤型に応じた装備を選ぶ事が必要です。散布作業時の適切な防護装備については、種々の安全性試験の結果に基づいて必要な装備が定められ、農薬のラベルに「安全使用上の注意」として表示されています。
低毒性農薬の普及や危害防止対策の進展にともない、使用者の中毒事故は減りましたが、それでも年間40件前後の「中毒事故」が報告されています。その多くは、注意事項を守らなかったことや、保管管理の不十分さが原因でした(表、グラフ)。
使用基準にしたがって
また、散布時に防護装備が必要なほど危険な農薬が使われるのだから、そのような農薬を使った農作物も危険ではないかという誤解があります。しかし、すでに述べたように防護装備は一時に多量の化学物質を浴びる「万が一」の危険性に備えるものです。農作物に付着し残留する農薬の量はわずかで、収穫までに分解したり雨や風に流れてごく微量になってしまいます。そして、このようなごく微量の農薬が残留した農作物を長年食べ続けた場合の健康被害を防ぐため、残留農薬基準が決められています。それに基づいた農薬使用基準により、実際の散布量や散布時期が定められ、残留農薬についての安全性が保証されているのです。
| 年次 | 死亡 ( )内は散布中 |
中毒 ( )内は散布中 |
|---|---|---|
| 1957~1960平均 | 45 | 681 |
| 1961~1965平均 | 38(20) | 322(296) |
| 1966~1970平均 | 39(15) | 276(252) |
| 1971~1975平均 | 21(4) | 233(216) |
| 1976~1980平均 | 17(6) | 158(147) |
| 1981~1985平均 | 12(3) | 68(59) |
| 1986~1990平均 | 6(3) | 54(45) |
| 1991~1995平均 | 4(1) | 20(13) |
| 1996~2000平均 | 2(0) | 52(41) |
| 2001~2005平均 | 4(1) | 64(54) |
| 2006 | 6(1) | 28(11) |
| 2007 | 0(0) | 35(26) |
| 2008 | 3(0) | 62(38) |
| 2009 | 3(0) | 76(42) |
| 2010 | 3(0) | 49(21) |
| 2011 | 8(0) | 40(18) |
| 2012 | 2(0) | 58(36) |
| 2013 | 4(0) | 30(12) |
| 2014 | 5(0) | 35(22) |
(注)1957年~1975年は厚生省薬務局監視指導課の調査による数値より平均値を求めたもの。
1976年以降は農林水産省(農産園芸局植物防疫課など)の調査による。
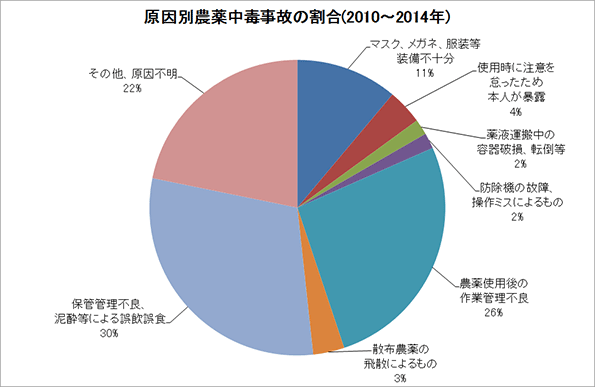
(2017年5月)
「JCPA農薬工業会」は、
「クロップライフジャパン」に名称を変更しました。
更新情報は、トップページのTOPICS一覧からご覧ください。
2024年9月頃、新サイトについてご案内します。
サイト切替までは変わらず本サイトをご利用いただけます。